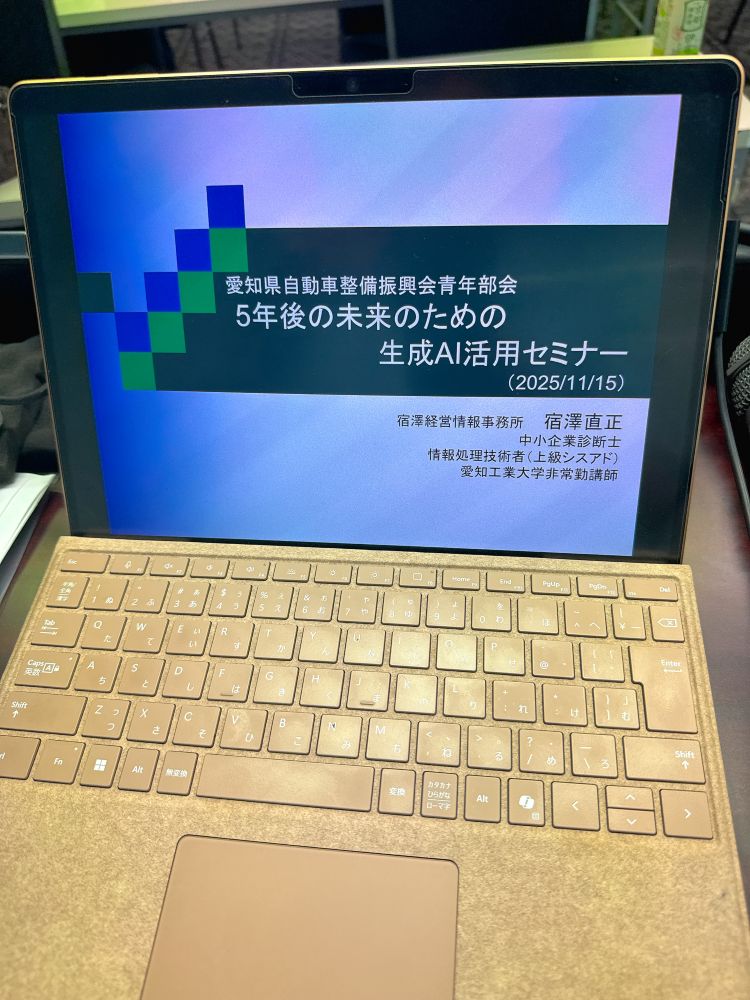愛知県自動車整備振興会青年部会のブロックセミナーで「5年後の未来のための生成AI活用セミナー」の話をしました。
たっぷりと約4時間頂けて、その間ワークなどもなしでひたすら話していました。
話す方はたくさん伝えられるのでワクワクですが、聴く方は地獄かも…と思いましたが問題はなかったようです。
もともと、参加しているみなさんは仲良しで、和気あいあいと楽しそうに話を聴いてくださいました。
自動車整備のどのような部分に生成AIが使えるのか…よくわからない部分もありました。
ただ、話を伺うと「自動車整備は車のドクター」という言葉がぴったり当てはまると勝手に思いました。
非常に緻密な仕事で「業務効率化」に生成AIを活用できる部分はたくさんありそうです。
それに加えて「情報発信」にすでに生成AIを使っている方も多かったようです。さらに「ノウハウ共有」にも使えそうです。
続く懇親会はもっと突っ込んだ質問が出て、本当に生成AIでいろいろな使い方をされていて、とても勉強になりました。
そして懇親会のときに「デジタルの人かと思ったらアナログの人なのですね」と言われました。すごく嬉しかったです。
「今回のパワポの資料は生成AIで作っていますか?」の質問が出たので、「いいえ」と答えました。
自分は研修やセミナーの資料には自分の想いを入れ込みたいので、デザインがやや画一化される生成AIは使わないことも話しました。
生成AIを使うのは悪いのではなく、それによって人としての個性が薄まってしまうのが嫌だったのです。
もちろん、自分が納得できる部分には、生成AIをどんどん使っていきたい推進派です。
今回の話には「生成AIの単なる使い方」の話にはしたくなかったです。
「生成AIとの向き合い方」を意識的にいれ、「自分自身を映し出す鏡」や「目標クリアをサポートする伴走者」などの話もしました。
生成AIは仕事を助けてくれるツールとしてだけではなく、心を調えたり、混乱の整理を手伝ってくれるパートナーだと思っています。
生成AIに問い掛ける時に無意識に敬語を使うのもその理由かもしれません。