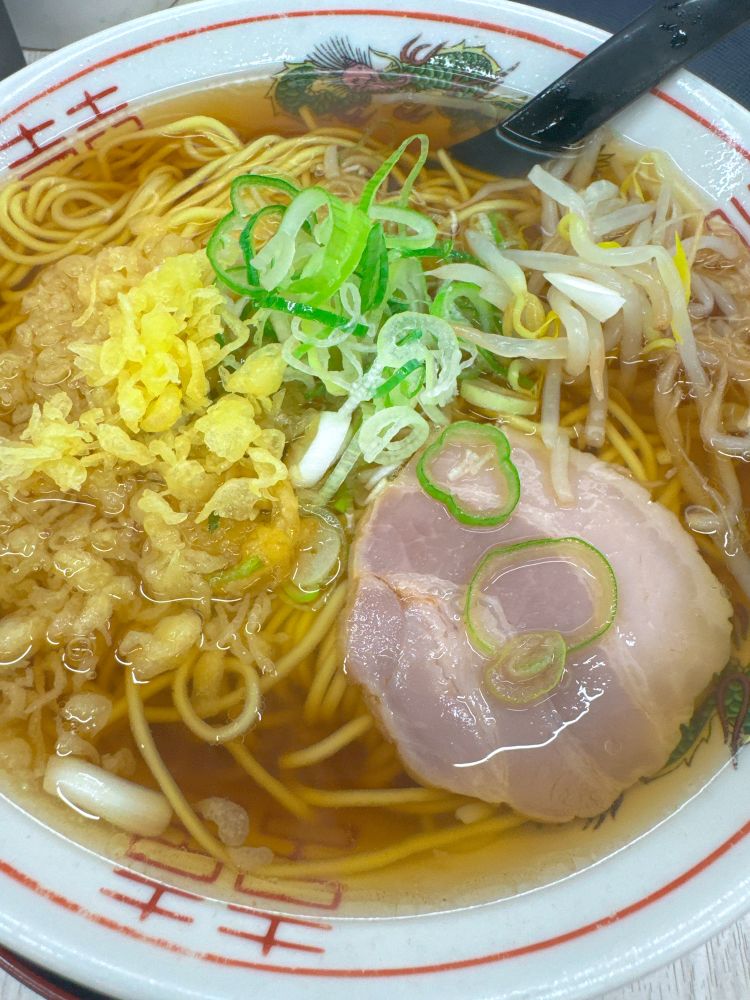午前中に生成AIによる「ビジネスプランのアイデア発想」研修のテキストレビューをしてもらいました。
この研修は2日間をかけて、ビジネスプランを作るアイデア発想を生成AIで行う体験してもらうもので楽しみです。
午後からは愛工大「インターネットビジネス活用」の第13講で、テーマは「生成AI」です。
生成AIはChatGPTが騒がれ始めた2023年に初めて2コマ大学講義で取り入れました。
当時は「ChatGPTって間違えるし使えないよね」「ChatGPTなんかを学生が使ったらダメになるよね」の風潮が大きかったです。
ただし、間違った使い方をするのは良くないと思い、あえて2コマを大学講義で取り入れました。
その当時はChatGPTを仕事でセミナーやましてや大学講義で取り入れている人もほとんどいなかったです。
「生成AIって最近よく聞くけど、何ができるの」という感じの学生ばかりで、使っている人もほとんどいませんでした。
それが昨年は、ほとんどの人が使っており一気に広まったと感じました。
ただ、正しい使い方は浸透する一方で、ただ単に「手を抜くため」だけに使ってしまっているような場合もありました。
ただ、今年は、活用スキルやその意識が格段に上がっていました。
演習では、どのようにChatGPTを使い、場合によってのプロンプトの工夫を書き出してもらい、それをグループで共有、他グループへのお勧めを検討してもらいました。
学生の発表からは「こういうキーワードを入れればこういう結果が返ってくる」というのがイメージできていました。
学生には素晴らしいプロンプトと伝える一方で、正しい生成AI活用で忘れてはいけないところも話をしました。
生成AIは責任を取ることができません。
なので、生成AIから出てきた回答を自分の腹に落として自分のものとしない限りは世に出してはいけないということです。
そのためにも、生成AIから出てきた結果を正しく疑うこと、つまりクリティカルシンキングのスキルが大切だと伝えました。
また、プロンプトではやはり論理的思考が必要です。
推論モデルにより、以前よりは論理的でなくてもプロンプトの意図を汲み取ってくれるようになってきています。
ただ、やはり背景や制約条件などをきちんと伝えるなどは変わらず重要です。